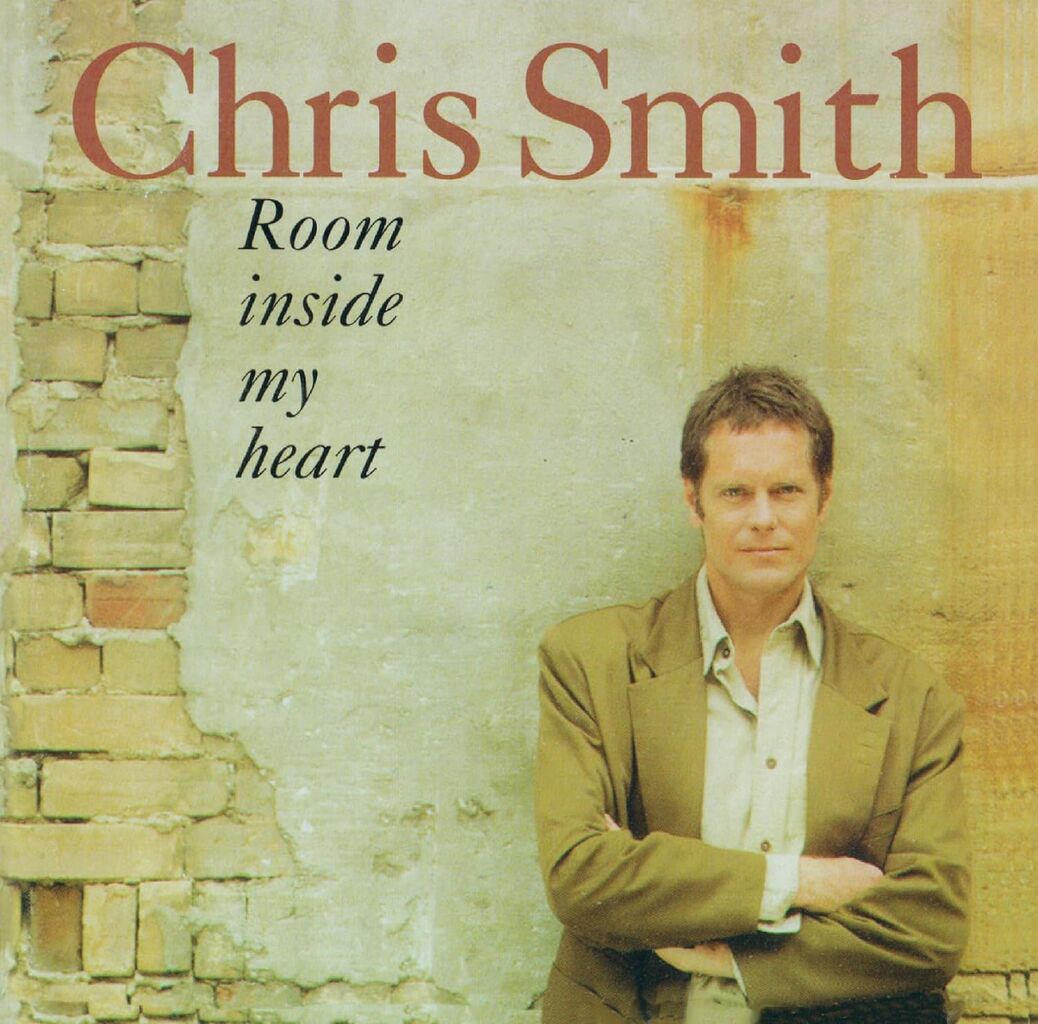盟友デヴィッド・リンドレーとのライヴ盤『LOVE IS STRANGE』が10年に出たものの、オリジナル新作ということでは、08年『TIME THE CONQUEROR(時の征者)』以来6年ぶりのニュー・アルバム。タイトルの『STANDING IN THE BREACH』とは、直訳では “裂け目に立つ” という意味で、この曲がハイチ地震(10年)をキッカケに書き始められたことを示している。
しかし、同時にこの言葉は、“難局に当たる” とか “攻撃の矢面に立つ” という意で使う慣用句でも。タイトル曲の訳詞を読んでいくと、地震はただの序章に過ぎず、詞は貧困や奴隷制度、民族紛争、宗教問題など、大きな視野でワイドに問題提議していく。まさにジャクソンの真骨頂たる曲だ。
こうした誠実で真摯な社会的メッセージを投げ掛けるのは、彼の十八番としてお馴染み。でもその主張を、よりダイレクトかつストレートに発するようになった80年代後半以降、彼の音楽は何かを失ってしまった気がしていた。確かにジャクソンの歌、ジャクソンの音楽は鳴っているのに、自分の心にはあまり響いて来なかった。
ところがこのアルバムは、何かが違う。原点回帰しているというか、言葉よりも まず歌と音で深く感情に訴えかけてくる。1曲目<The Birds Of St. Marks>なんて、まさにそう。この曲はジャクソンが駆け出しの頃ニコのために書いたが、そのまま陽の目を見ず、ずっと眠っていた曲なのだ。それを05年の『SOLO ACOUSTIC Vol.1』で弾き語り、今度はバンド・アレンジで再演した。何でもニコがロジャー・マッギンのファンだったことから、元々バーズのイメージで書いたらしく、今回はそれを踏襲。デヴィッド・クロスビーにもアドヴァイスを乞うたそうだから、そりゃあ本格的である。
ロブ・ワッサーマンが持って来たウッディ・ガスリーの詞に曲を付けた<You Know The Night>、イーグルスに提供した<Take It Easy>に登場する街ウィンズローを再訪して書いた<Leaving Winslow>、そして最後は、妻を自殺で失なう精神科医を描いた映画『SHRINK』(09年)への提供曲<Here>で締め括る。かつての彼自身の境遇に似た、極めてパーソナルなエピローグだ。
バックには、ジム・ケルトナー(ds)やボブ・グラウブ(b)、ベンモント・テンチ(kyd)、マーク・ゴールデンバーグ(g)といった古株常連から、ヴェニスのキップ・レノン(cho)、ドーズのテイラー&グリフィン・ゴールドスミス(cho)、タル・ウィルケンフェルド(b)といった新顔まで、幅広いミュージシャンが参加している。この辺りも、素直に初期の音に回帰できた遠因だろうか。
そこで思い出したのが、この春に発売されたジャクソンへのトリビュート・アルバム『LOOKING INTO YOU』だ。ドン・ヘンリーとブルース・スプリングスティーンを筆頭に、J.D.サウザー、ボニー・レイット、カーラ・ボノフ、ブルース・ホーンビー、ルシンダ・ウィリアムス、ベン・ハーパー、ケブ・モー等など、まさに有名どころが参加し、ジャクソンの作品23曲をカヴァーしている。
それをオリジナルと比べて、どちらが優れているか?なんて論議したって、何も始まらない。原曲に忠実に歌う者、自分の解釈で歌う者、どちらも彼らなりのジャクソンへのリスペクトなのだから、それを素直に楽しめばいいではないか。そこにヴェニスの名を見つけ、新作にもキップ・レノンが参加しているところを見ると、きっとジャクソンもコレを楽しんだのだろう。ただし選曲は、数曲を除いて70年代のアルバムに集中している。ジャケットの写真も、2nd『FOR EVERYMAN』にあしらわれた子供の頃の家。つまりは、そういうコトなのだ。
このトリビュートとジャクソン自身の原点回帰は、おそらく直接連動したモノではないだろう。でもそのラインナップを見た時、ジャクソンにも “やっぱりそうか…” 的な感覚があったのではないか。
この久々の快作を引っ提げ、来年3月に来日が決まったジャクソン。今度は観に行こうかなぁ!と思っていたら、ナンとその前月に弟セヴェリン・ブラウンとスティーヴ・ヌーナンの公演まで決定し、かなりビックリ ちなみに前述の家には、現在このセヴェリンが住んでいるそうです。
ちなみに前述の家には、現在このセヴェリンが住んでいるそうです。
こうした誠実で真摯な社会的メッセージを投げ掛けるのは、彼の十八番としてお馴染み。でもその主張を、よりダイレクトかつストレートに発するようになった80年代後半以降、彼の音楽は何かを失ってしまった気がしていた。確かにジャクソンの歌、ジャクソンの音楽は鳴っているのに、自分の心にはあまり響いて来なかった。
ところがこのアルバムは、何かが違う。原点回帰しているというか、言葉よりも まず歌と音で深く感情に訴えかけてくる。1曲目<The Birds Of St. Marks>なんて、まさにそう。この曲はジャクソンが駆け出しの頃ニコのために書いたが、そのまま陽の目を見ず、ずっと眠っていた曲なのだ。それを05年の『SOLO ACOUSTIC Vol.1』で弾き語り、今度はバンド・アレンジで再演した。何でもニコがロジャー・マッギンのファンだったことから、元々バーズのイメージで書いたらしく、今回はそれを踏襲。デヴィッド・クロスビーにもアドヴァイスを乞うたそうだから、そりゃあ本格的である。
ロブ・ワッサーマンが持って来たウッディ・ガスリーの詞に曲を付けた<You Know The Night>、イーグルスに提供した<Take It Easy>に登場する街ウィンズローを再訪して書いた<Leaving Winslow>、そして最後は、妻を自殺で失なう精神科医を描いた映画『SHRINK』(09年)への提供曲<Here>で締め括る。かつての彼自身の境遇に似た、極めてパーソナルなエピローグだ。
バックには、ジム・ケルトナー(ds)やボブ・グラウブ(b)、ベンモント・テンチ(kyd)、マーク・ゴールデンバーグ(g)といった古株常連から、ヴェニスのキップ・レノン(cho)、ドーズのテイラー&グリフィン・ゴールドスミス(cho)、タル・ウィルケンフェルド(b)といった新顔まで、幅広いミュージシャンが参加している。この辺りも、素直に初期の音に回帰できた遠因だろうか。
そこで思い出したのが、この春に発売されたジャクソンへのトリビュート・アルバム『LOOKING INTO YOU』だ。ドン・ヘンリーとブルース・スプリングスティーンを筆頭に、J.D.サウザー、ボニー・レイット、カーラ・ボノフ、ブルース・ホーンビー、ルシンダ・ウィリアムス、ベン・ハーパー、ケブ・モー等など、まさに有名どころが参加し、ジャクソンの作品23曲をカヴァーしている。
それをオリジナルと比べて、どちらが優れているか?なんて論議したって、何も始まらない。原曲に忠実に歌う者、自分の解釈で歌う者、どちらも彼らなりのジャクソンへのリスペクトなのだから、それを素直に楽しめばいいではないか。そこにヴェニスの名を見つけ、新作にもキップ・レノンが参加しているところを見ると、きっとジャクソンもコレを楽しんだのだろう。ただし選曲は、数曲を除いて70年代のアルバムに集中している。ジャケットの写真も、2nd『FOR EVERYMAN』にあしらわれた子供の頃の家。つまりは、そういうコトなのだ。
このトリビュートとジャクソン自身の原点回帰は、おそらく直接連動したモノではないだろう。でもそのラインナップを見た時、ジャクソンにも “やっぱりそうか…” 的な感覚があったのではないか。
この久々の快作を引っ提げ、来年3月に来日が決まったジャクソン。今度は観に行こうかなぁ!と思っていたら、ナンとその前月に弟セヴェリン・ブラウンとスティーヴ・ヌーナンの公演まで決定し、かなりビックリ
 ちなみに前述の家には、現在このセヴェリンが住んでいるそうです。
ちなみに前述の家には、現在このセヴェリンが住んでいるそうです。