

昨日のポストはブルーノートLAというジャズ・フュージョンの大メジャー・レーベルもののコンピだったが、今日は同路線のマイナーものを。77年〜80年の僅か3年間、ニューヨークからユニークなクロスオーヴァー・サウンドを発信した幻のレーベル:ヴァーサタイルの作品群が一挙10枚、日本初CD化を含むカタチで復刻された。その中から、まずは当ブログのお客様が一番馴染みのありそうなところをピックアップしてご紹介。スタッフのギタリストとして名を挙げたテキサス・ファンクの雄、コーネル・デュプリーの2作である。
デュプリーのソロというと、何はさておき74年の初ソロ作『TEASIN'』が思い浮かぶ。リチャード・ティー、チャック・レイニー、バーナード・パーディにバックアップされたソレが彼の代表作であることは、今以て論を俟たない。でもデュプリーの朴訥とした激渋ギターを聴きたい人には、このヴァーサタイルからの2枚も無視厳禁だ。
77年末にレコーディングされた『SATURDAY NIGHT FEVER』は、サックスのアレックス・フォスター、同じくヴァーサタイルにソロ作を残すベースのバスター・ウィリアムスなど、ニューヨーク録音ながら少々渋い顔ぶれによる録音。スタッフ全盛期だから、敢えて周辺メンバーを遠ざけた気がするが、やっぱりコレをその人脈でやっていたら…と、脳内再生してしまう。ビー・ジーズ絡みの<Stayin' Alive>と<How Deep Is Your Love>、ヒートウェイヴ<Boogie Nights>あたりはディスコ仕様に見えるが、ギターは完全にデュプリー節。リンダ・ロンシュタットがヒットさせた<It's So Easy>もまた然り。こうした直近の話題曲やヒット・チューンをネタにするのは、イージー・リスニング的側面があるクロスオーヴァー/フュージョンでは珍しいことではないし、デュプリーはあまり曲を書かないという裏事情もある。それでもこのアートワークで分かるように、このチョイスはちょっと安直すぎ。おそらくデュプリー自身はビル・ウィザース<Lovely Day>やドラマティックス<Shake It Well>に共鳴していたと思われるから尚更だ。ポール・サイモン<Slip Slidin' Away>では、原曲に参加していたであろうスタッフの同僚たちへの対抗意識もあっただろう。何をやってもオレ様流儀に引っ張り込む磁場があるのだから、無闇にハヤリ物に手を出しすイメージは、返ってマイナスじゃないかと思うが…。
その8ヶ月後に制作された『SHADOW DANCING』も、基本的なコンセプトは同じ。<Shadow Dancing / Last Dance>は、ビー・ジーズとドナ・サマーのヒットをメドレーにしたもので、ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ<The Closer I Get To You>、スティーヴン・ビショップ<On And On>、キャロル・キング・クラシック<Hey Girl>、スティーリー・ダン<Peg>、ドリー・パートン<Two Doors Down>などが並ぶ。ラストの<The Creeper>のみデュプリー自作。でもどんな曲を演っても、最初のテーマをなぞるだけで、アドリブ・ソロに入ってしまえばみな同じ。それがデュプリーのオレ様流だ。こちらのバックには、クリス・パーカーとウィル・リーがリズム隊で参加し、ハンク・クロフォードもサックスを吹く。ゆらめきのエレキ・ピアノはジミー・スミスとクレジットされているが、おそらくはリチャード・ティー没後にスタッフに関わったジェイムス・アレン・スミスだろう。
同じ黒人のジャズ・ギタリストでも、デヴィッド・T・ウォーカーの上品さとは違うし、ベースもこなすフィル・アップチャーチの器用さは持ち合わせていない。でも、そのパキンパキンのテレキャスターは、いつどんなアレンジに乗せられようと、いつだって同じ匂いを放つ。たったひとつの芸風で渡世を渡る、これもまた職人の在り方。その燻し銀のギターが、ダニー・ハサウェイやアレサ・フランクリンらに愛された。
77年末にレコーディングされた『SATURDAY NIGHT FEVER』は、サックスのアレックス・フォスター、同じくヴァーサタイルにソロ作を残すベースのバスター・ウィリアムスなど、ニューヨーク録音ながら少々渋い顔ぶれによる録音。スタッフ全盛期だから、敢えて周辺メンバーを遠ざけた気がするが、やっぱりコレをその人脈でやっていたら…と、脳内再生してしまう。ビー・ジーズ絡みの<Stayin' Alive>と<How Deep Is Your Love>、ヒートウェイヴ<Boogie Nights>あたりはディスコ仕様に見えるが、ギターは完全にデュプリー節。リンダ・ロンシュタットがヒットさせた<It's So Easy>もまた然り。こうした直近の話題曲やヒット・チューンをネタにするのは、イージー・リスニング的側面があるクロスオーヴァー/フュージョンでは珍しいことではないし、デュプリーはあまり曲を書かないという裏事情もある。それでもこのアートワークで分かるように、このチョイスはちょっと安直すぎ。おそらくデュプリー自身はビル・ウィザース<Lovely Day>やドラマティックス<Shake It Well>に共鳴していたと思われるから尚更だ。ポール・サイモン<Slip Slidin' Away>では、原曲に参加していたであろうスタッフの同僚たちへの対抗意識もあっただろう。何をやってもオレ様流儀に引っ張り込む磁場があるのだから、無闇にハヤリ物に手を出しすイメージは、返ってマイナスじゃないかと思うが…。
その8ヶ月後に制作された『SHADOW DANCING』も、基本的なコンセプトは同じ。<Shadow Dancing / Last Dance>は、ビー・ジーズとドナ・サマーのヒットをメドレーにしたもので、ロバータ・フラック&ダニー・ハサウェイ<The Closer I Get To You>、スティーヴン・ビショップ<On And On>、キャロル・キング・クラシック<Hey Girl>、スティーリー・ダン<Peg>、ドリー・パートン<Two Doors Down>などが並ぶ。ラストの<The Creeper>のみデュプリー自作。でもどんな曲を演っても、最初のテーマをなぞるだけで、アドリブ・ソロに入ってしまえばみな同じ。それがデュプリーのオレ様流だ。こちらのバックには、クリス・パーカーとウィル・リーがリズム隊で参加し、ハンク・クロフォードもサックスを吹く。ゆらめきのエレキ・ピアノはジミー・スミスとクレジットされているが、おそらくはリチャード・ティー没後にスタッフに関わったジェイムス・アレン・スミスだろう。
同じ黒人のジャズ・ギタリストでも、デヴィッド・T・ウォーカーの上品さとは違うし、ベースもこなすフィル・アップチャーチの器用さは持ち合わせていない。でも、そのパキンパキンのテレキャスターは、いつどんなアレンジに乗せられようと、いつだって同じ匂いを放つ。たったひとつの芸風で渡世を渡る、これもまた職人の在り方。その燻し銀のギターが、ダニー・ハサウェイやアレサ・フランクリンらに愛された。







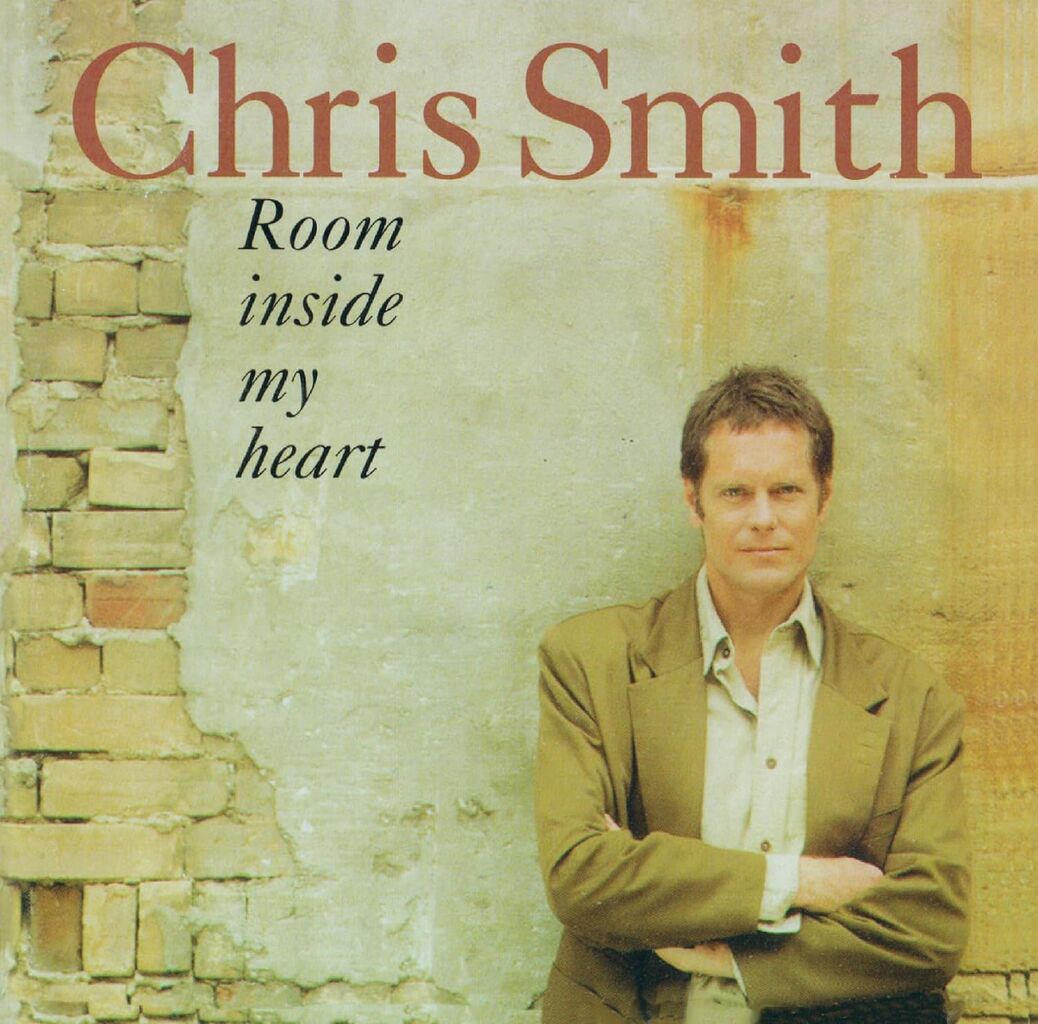
























「Shadow Dancing」は意外に良い。
本サイト的な興味は「Peg」でしょうが
これがまるでカントリーソングの様。
速く演るとこーなっちゃうんだ。
この曲だけは残念、頂けません。