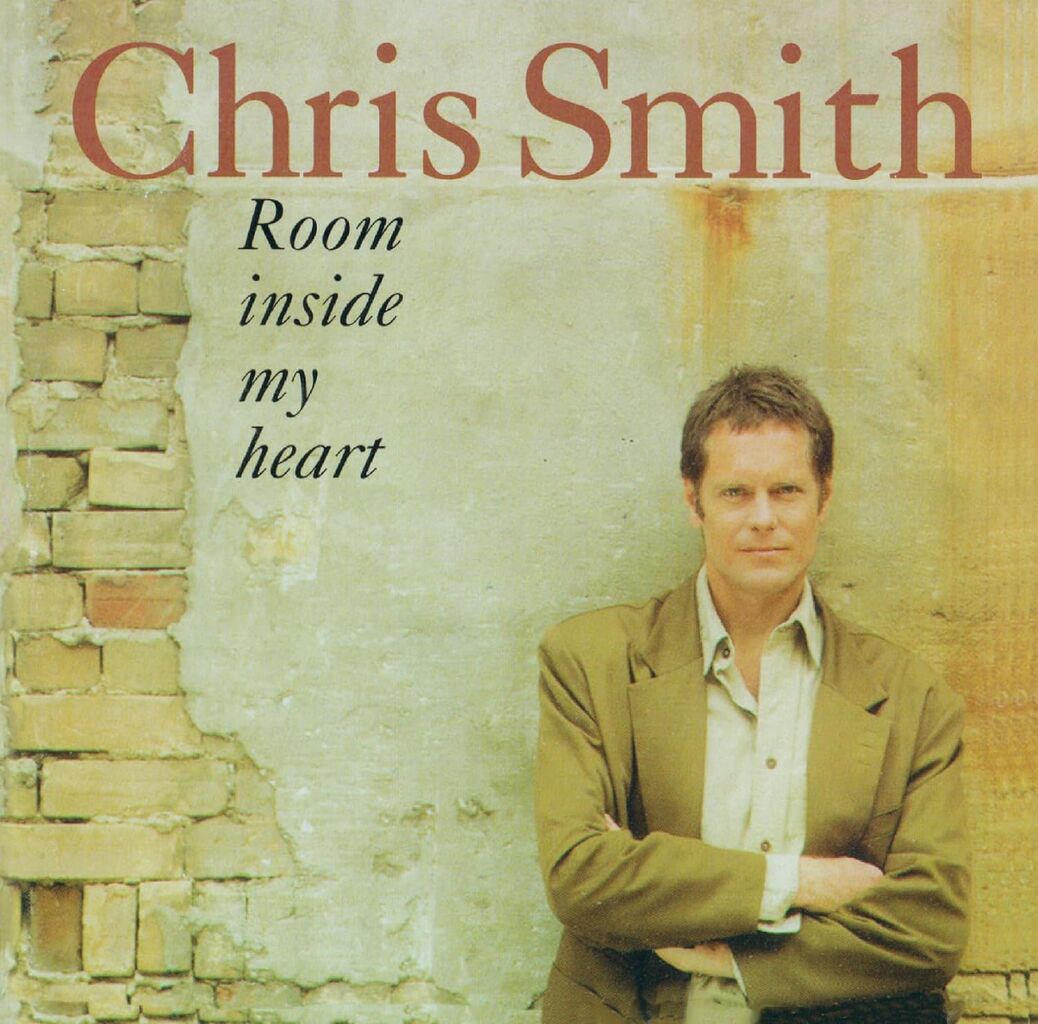この処、朝のウォーキングのBGMでよく聴くのが、AC/DC奇跡の新作『PWR UP(POWER UP)』。こういうアルバムを聴きながら抜けるような秋空の下を足早に歩いていると、気分爽快、エラく元気が出る。まさに『PWR UP』そのままだが、6年前の前作『ROCK OR BUST』を出した後には、様々なトラブルが次々発生。5人のメンバーのうち3人が不在となり、バンドの存続さえ危ぶまれていたのだ。
まずドラマーのフィル・ラッドが不祥事を起こし収監。ワールド・ツアー中はヴォーカルのブライアン・ジョンソンが聴覚障害で離脱し(代役は自ら志願したアクセル・ローズ)、ツアー終了するとベースのクリス・ウィリアムスが引退表明。そして最後は17年11月、アンガス・ヤングと共にバンドを牽引してきたマルコム・ヤングが他界した(享年64)。『ROCK OR BUST』では既にメンバーから外れ、甥スティーヴ・ヤングにリズム・ギターを委ねつつ、自らはアンガスと曲作りに専念するようになっていたマルコム。でもAC/DCサウンドの要だったリフ・メイクは彼の手に拠る部分が大きかったから、その喪失感は途轍もなくデカかった。
でもだからこそ、残されたメンバーたちが心をイツにしたのだろう。アンガスとスティーヴの元、ブライアン、フィル、クリフの3人がカムバック。この6年部りの新作『POWER UP』を完成させる。作曲は全曲アンガスとマルコムの共作。生前マルコムが残していたモチーフを元に、アンガスがアイディアを引き継いで完成させたのだと言う。プロデュースも前2作に続きブレンダン・オブライエン。結果として、マルコムのロック魂をみんなで引き継いだ、半ば決意表明のようなアルバムになった。
日本にAC/DCが紹介されたのは、77年作『LET THERE BE ROCK(ロック魂)』が最初。カナザワもその時に初めてAC/DCを聴いたが、既にジューダス・プリーストのようなドラマチックでスピード感のあるハード・ロックを聴いていた(当時まだメタルっぽくなかった)ため、シンプルで足踏みするようなハード・ブギー・サウンドのAC/DCには、あまり食指が動かなかった。米国人気の盛り上がりと共に耳を傾けたが、90年代はほぼスルーしていたのが正直なところである。
それなのに、『BLACK ICE』や『ROCK OR BUST』を聴いた時に、滅茶めちゃデジャ・ヴー感があって。今回の『PWR UP』もそう。恐ろしいくらいに、な〜んにも変わってない。そりゃあ旧作を発売順に聴いていけば、彼らなりの進化やマイナー・チェンジがあっただろう。全米制覇の頃は、作品のスケール感も大きくなった。でも一般的水準では、そんなサウンドの変化など まるでナシ。そうした永遠のマンネリズム、一芸が武器になっている点では、ローリング・ストーンズと並んで双璧と言える。ファンも彼らに変化など求めていないワケで、AC/DCらしくあることが一番重要なのだ。
気分がヨレてきた時は、元気一発 AC/DC


でもだからこそ、残されたメンバーたちが心をイツにしたのだろう。アンガスとスティーヴの元、ブライアン、フィル、クリフの3人がカムバック。この6年部りの新作『POWER UP』を完成させる。作曲は全曲アンガスとマルコムの共作。生前マルコムが残していたモチーフを元に、アンガスがアイディアを引き継いで完成させたのだと言う。プロデュースも前2作に続きブレンダン・オブライエン。結果として、マルコムのロック魂をみんなで引き継いだ、半ば決意表明のようなアルバムになった。
日本にAC/DCが紹介されたのは、77年作『LET THERE BE ROCK(ロック魂)』が最初。カナザワもその時に初めてAC/DCを聴いたが、既にジューダス・プリーストのようなドラマチックでスピード感のあるハード・ロックを聴いていた(当時まだメタルっぽくなかった)ため、シンプルで足踏みするようなハード・ブギー・サウンドのAC/DCには、あまり食指が動かなかった。米国人気の盛り上がりと共に耳を傾けたが、90年代はほぼスルーしていたのが正直なところである。
それなのに、『BLACK ICE』や『ROCK OR BUST』を聴いた時に、滅茶めちゃデジャ・ヴー感があって。今回の『PWR UP』もそう。恐ろしいくらいに、な〜んにも変わってない。そりゃあ旧作を発売順に聴いていけば、彼らなりの進化やマイナー・チェンジがあっただろう。全米制覇の頃は、作品のスケール感も大きくなった。でも一般的水準では、そんなサウンドの変化など まるでナシ。そうした永遠のマンネリズム、一芸が武器になっている点では、ローリング・ストーンズと並んで双璧と言える。ファンも彼らに変化など求めていないワケで、AC/DCらしくあることが一番重要なのだ。
気分がヨレてきた時は、元気一発 AC/DC